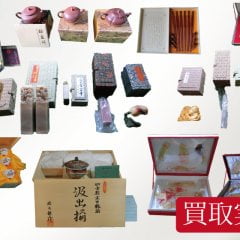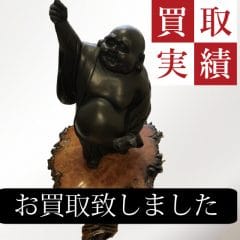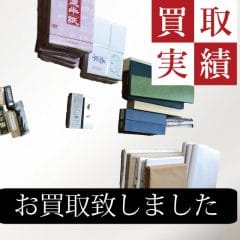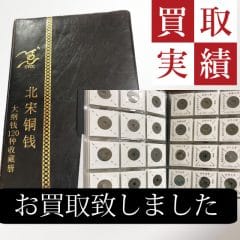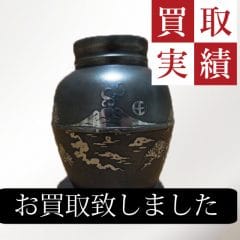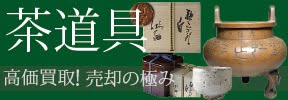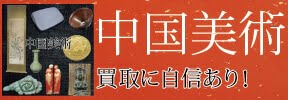日本の器大百科|磁器・陶器の差と産地ごとの性質まとめ|焼き物リスト

有田焼/伊万里焼

有田焼・伊万里焼は佐賀県などで作られています。
透明性のある白磁が魅力的で、その上に煌びやかな絵付けがなされていることでも高く評価されています。
堅く、ガラスを思わせる滑らかさがあり、軽く薄いため、日用品としての需要も高いです。
16世紀頃の朝鮮出兵の折に我が国に来た職人が、陶石を有田泉山で見つけ、磁器の制作をスタートしたのが発祥と有田焼・伊万里焼の発祥とされています。
実はこれが国内最初の磁器であると言われており、今も日本有数の磁器の産地として知られています。
「有田焼」とも「伊万里焼」とも言いますが、近年では「有田焼」という言い方のほうが国内外で広く知られています。
また、以前は有田焼の出荷が伊万里港から行われていたことが、「伊万里焼」というネーミングの由来となっています。
産地:佐賀県西松浦郡有田町、嬉野市、武雄市、伊万里市など
産地情報
| 名称 | 佐賀県陶磁器工業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒844-0026 佐賀県西松浦郡有田町外尾町丙1217 |
唐津焼

佐賀県などで作られています。
昔から焼き物の産地として知られており「一楽二萩三唐津」「東は瀬戸物、西は唐津物」という言い回しさえあるくらいです。
16世紀辺りには、唐津焼の制作がスタートしていたと見られています。
簡素で味わい深い雰囲気であるがゆえに、特に茶の湯の界隈で愛されていました。
また、唐津焼には関しては、「使用してもらってこそ出来上がる」という意味の「作り手八分、使い手二部」という表現もあります。
いわゆる「用の美」です。
産地:佐賀県杵島郡白石町、西松浦郡有田町、東松浦郡玄海町、武雄市、嬉野市、伊万里市、多久市、唐津市など
産地情報
| 名称 | 唐津焼協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒847-0816 佐賀県唐津市新興町2881-1 ふるさと会館アルピノ2階 |
三川内焼

長崎県などで作られています。
ことに唐子絵で知られている磁器であり、藍色の呉須で白磁に模様が施されます。
細やかで微細な絵柄の三川内焼が、普段使いの食器としても鑑賞用の高級品としても出回っています。
また、光を通すレベルで薄い「卵殻手」や「透かし彫り」などと呼ばれる技法が程子されているのも魅力的です。
平戸藩主の松浦鎮信が17世紀初頭に、焼き物の制作をスタートさせたのが三川内焼の発祥と見られています。
それから、平戸藩の御用窯として明治維新の頃まで重宝されました。
産地:長崎県佐世保市など
産地情報
| 名称 | 三川内陶磁器工業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒859-3151 長崎県佐世保市三川内本町343 三川内焼伝統産業会館内 |
波佐見焼

長崎県などで作られています。
90近くの窯元が産地に存在しており、労働者の40パーセントほどが器制作に関わっています。
16世紀終盤に質の高い陶石が発見されたことから、大村藩主の大村喜前が登り窯を作らせたのが波佐見焼の発祥であるとされています。
最初は陶器がメインでしたが、だんだんと磁器作りに移行していきます。
一般庶民向けのリーズナブルかつスタイリッシュな器を大量生産することにより、産地をどんどん成長させていきました。
最初は、波佐見では有田焼の下請けを引き受けていましたが、今ではオリジナルの波佐見焼作りがメインとなっています。
産地:長崎県東彼杵群東彼杵町、波佐見町、川棚町など
産地情報
| 名称 | 波佐見陶磁器工業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒859-3711 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2239 |
ブロックマグ HASAMI

このマルヒロのブロックマグは、スタッキング可能なユニークなフォルムと鮮やかなカラーリングが魅力的な商品であり、コンプリートを目指している方もたくさんいるそうです。
呉須の藍色で施される絵付けや、透明感の高い白磁の美しさなどで、波佐見焼は高く評価されています。
また、大量生産されてもいたので、人気商品がいくつもあります。
少し紹介していきましょう。
くらわんか椀

「くらわんか椀」というネーミングは「くらわんか船」から来ています。
この船が来る大阪の船着き場にて、「餅くらわんか(食べませんか?)酒くらわんか」と声をかけながら商人が練り歩いていたそうです。
高台が重いので、船の中で使っても倒れにくいです。
くわらんか椀はその安価さによって人気を博しました。
「磁器は高額である」という常識を覆す品物となったようです。
コンプラ瓶

シンプルな染付白磁であり、酒や醤油を入れた状態で輸出されていました。
酒や醤油などとアルファベットで文字を入れることで、中身が何なのかを分かるようにしていたというユニークな焼き物です。
ルイ14世やトルストイもコンプラ瓶のファンだったそうです。
小代焼(小岱焼)

熊本県などで作られています。
柄杓などで笹や藁の灰から作った黄色釉や白釉を流しかけるという方法で制作される陶器です。窯の温度や釉薬によって色が変わります(飴小代、白小代、黄小代、青小代など)。
17世紀の辺りにはすでに作られていました。
高温で焼くため頑丈であり、日用品がたくさん制作されています。
産地:熊本県玉名郡長洲町、玉名郡南関町、宇城市、熊本市、荒尾市など
産地情報
| 名称 | 小代焼窯元の会 |
|---|---|
| 住所 | 〒864-0166 熊本県荒尾市府本1712-2 小岱焼末安窯 内 |
天草陶磁器

熊本県などで作られています。
「天草陶磁器」という焼き物が存在しているわけではなく、丸尾焼・水の平焼・高浜焼・内田皿山焼などの陶磁器を総じて「天草陶磁器」と呼びます。
歴史が最も深いのは17世紀頃に登場した内田皿山焼です。
18世紀辺りに丸尾焼と高浜焼が誕生して、昭和2年に水の平焼きが作られるようになりました。
天草地域の質の高い陶土と陶石が素材となっていますので、ハイクオリティーであり需要が大きいです。
釉薬を二重掛けする形式の陶器であり、黒釉やナマコ釉など、ユニークなものも登場しています。
磁器に関しては、作灰や白磁を用いた庶民的な風合いのものなどが作られています。
産地:熊本県天草郡苓北町、天草市、上天草市、本渡市など
産地情報
| 名称 | 天草陶磁振興協議会 |
|---|---|
| 住所 | 〒863-2505 熊本県天草郡苓北町内田554-1 (有)木山陶石鉱業所 内 |
薩摩焼

鹿児島県などで作られています。
陶磁器であり、基本的に磁器、黒薩摩、白薩摩といった3種類の製品で構成されています。
薩摩藩主の島津義弘が、16世紀の終盤に慶長の役のときに職人たちを連れてきて、地元で窯を作ったのが薩摩焼の発祥とされています。
パリ万博(1867)年に出展されたことで国外でも人気になり、より多くの人に知られるようになりました。
薩摩焼は2つに大別されます。
具体的に言うとリーズナブルな「黒もん(黒薩摩)」と、高級感のある「白もん(白薩摩)」という陶器に分かれています。
そこからさらに窯場によって、
磁器系
西餅田系
龍門司系
堅野系
苗代川系
の5種類に区分されます。
ただし、磁器系と西餅田系はもう残存していません。
産地情報
| 名称 | 鹿児島県薩摩焼協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒899-3101 鹿児島県日置市日吉町日置5679 |
壺屋焼

沖縄で作られている「沖縄感」の強い焼き物です。
焼き物のことを沖縄では「やむちん」と呼びます。
「壺屋やむちん通り」というところが那覇市には存在しており、そこには窯元が十数件もあります。
そして、壺屋焼が国の伝統工芸品認定を受けていますので、
沖縄の焼き物の代表格であると言えるでしょう。
壺屋焼には「上焼(じょうやち)」という釉薬を使って絵付けもするタイプの焼き物と、釉薬を使わない「荒焼(あらやち)」というタイプのものがあります。
さらに、「壺屋焼」は壺屋で制作される焼き物のことを指し、沖縄県の焼き物を総じて「やむちん」と呼んでいるわけです。
読谷山(ゆんたんざ)のやむちん
60以上の窯元が読谷山に存在しており、ここで制作させる焼き物を指して「読谷山焼」と言うこともあります。
特に人気の高い「北窯」と呼ばれる窯には工房が4件入っており、二十数名の弟子と四名の親方が、一緒に大きな窯で焼き物を制作しています。
この北窯が読谷山で一番大きいものであり、現在も1日平均で200~300個にのぼる焼き物が生産されています。
大きな窯の場合は、焼くのに72時間、温度が下がるまでに72時間を要するようです。
それから、沖縄のやむちんには素焼きを行わないものが多いです。
その代わりに「生掛け」と呼ばれる、「天日干しを施して、そのまま化粧土をかける」という方法が採用されています。
また、白色の輪が器の真ん中の辺りにあるのも特徴的です。
あえてこの輪を作ることで、器を重ねた状態で焼くことが可能になるのです。
これにより大量生産をして、リーズナブルな価格で流通させているということです。
読谷山焼の変遷
沖縄県で最初に人間国宝認定を受けた陶工の金城次郎が、読谷山で暮らし始めたことにより、読谷山で焼き物制作がスタートしたと言われています。
それまでは主に那覇で焼き物が制作されていたようですが、だんだんと読谷山での焼き物制作も盛んになっていきます。
平成4年には4名の親方によって、先ほど紹介された北窯が誕生しました。
壺屋焼の歴史と性質
17世紀辺りに今の壺屋焼のようなものが制作されるようになったと見られています。
焼物の産地として沖縄でもトップクラスに栄えましたが、明治維新が過ぎたあたりからだんだん勢いを失っていきます。
ですが柳宗悦たちの民芸運動の効果などにより、もう一回注目され、需要が復活しました。
壺屋焼には主に「上焼」と「荒焼」の2タイプがあります。
釉薬を使わずに焼くというのが荒焼の特徴であり、焼き締めたらマンガンを加えてさらに焼きます。
シーザーの置物、酒瓶、水瓶なども荒焼で制作されたものが大半です。
産地情報
| 名称 | 壺屋陶器事業協同組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒902-0065 沖縄県那覇市壷屋1-21-14 |
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
「日本の器大百科|磁器・陶器の差と産地ごとの性質まとめ|焼き物リスト」をご紹介しました。
家の中に眠っている、ガラクタだと思っていたものが、実は高値の付く貴重な骨董品かもしれません。
心当たりがありましたら、一度は鑑定士に見てもらうことをおすすめします。
「福和堂」では、経験豊富な鑑定士がお客様の骨董品をはじめ、茶道具や美術品など、さまざまな物品を査定いたします。一つ一つ丁寧に査定をおこない買取致します。ぜひご相談ください。




骨董美術品の買取 福和堂のサービス&コンテンツ
福和堂では骨董品、美術品、書道具、茶道具、銀製品、食器、古書、古道具、絵画、民芸品、書道具、花器、時計、贈答品、雑貨などの買取にも力を入れております。家の中に眠っている、ガラクタだと思っていたもの整理をお考えの方がいましたら、ぜひ「骨董買取の福和堂」にお任せ下さい。
お問い合わせ

遺品の整理の際はお声がけ下さい。WEBからのお問合せ・ご相談・お見積りは無料です。メールフォームに写真を添付していただくと大よその査定額をお伝えできます。